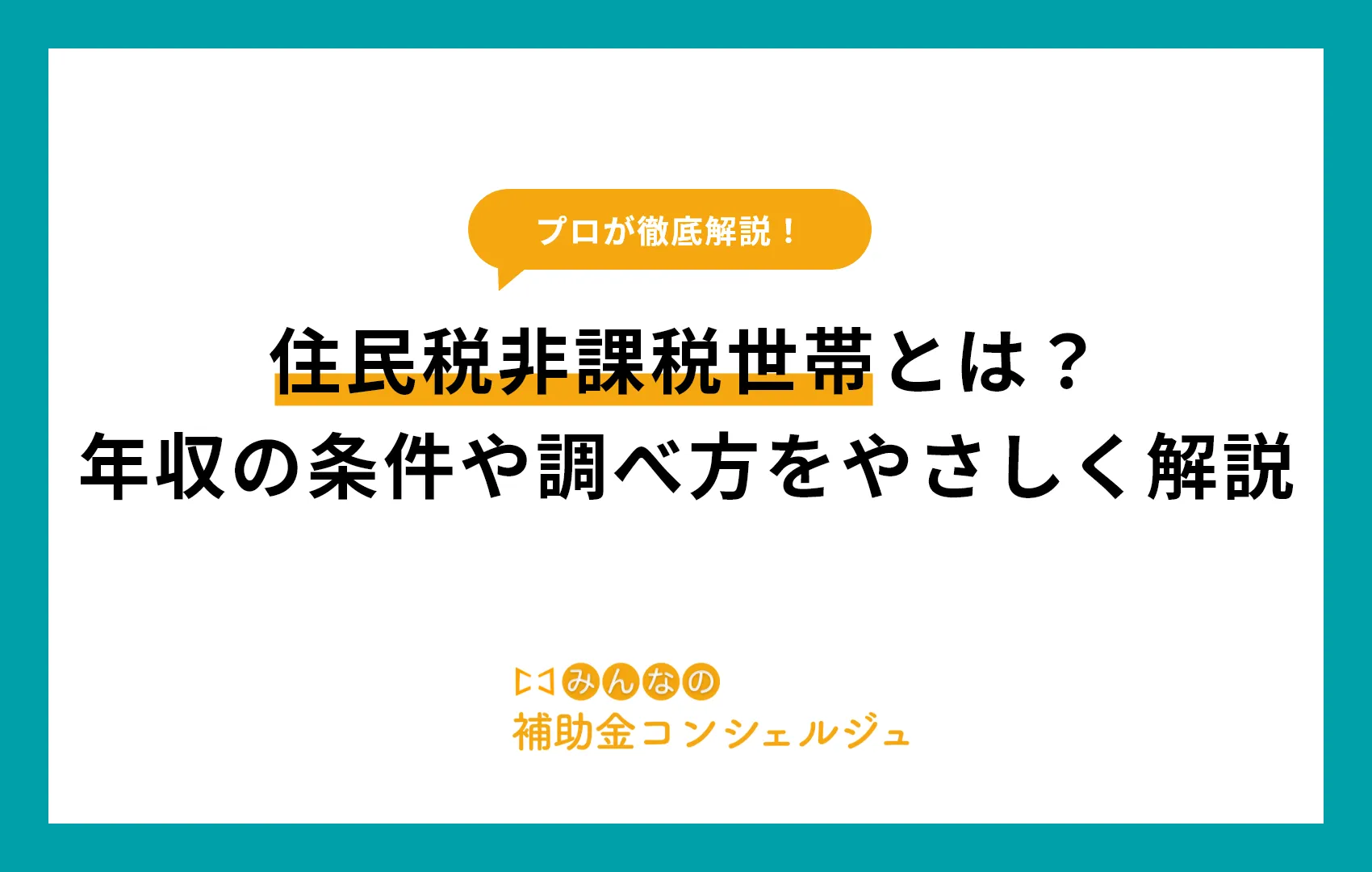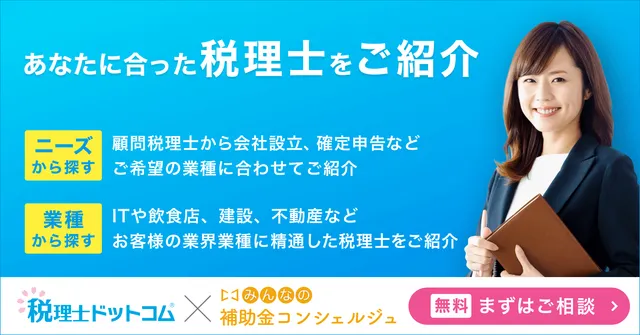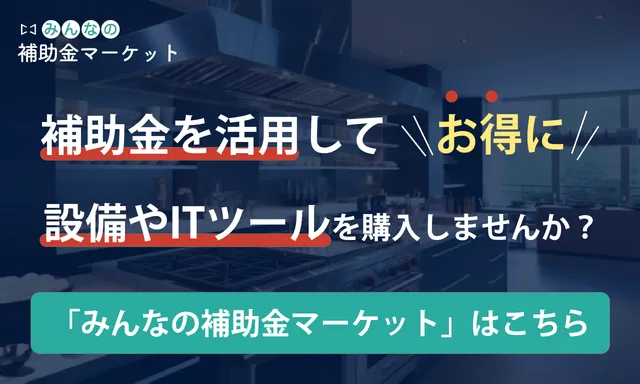住民税非課税世帯とは?年収の条件や調べ方をやさしく解説
政府は低所得者世帯に向けた支援をすることがあります。
その対象となる低所得世帯である住民税非課税世帯とは何でしょうか?
本コラムではその基準について分かりやすく解説します。
該当していれば給付金を受給できる可能性があります!
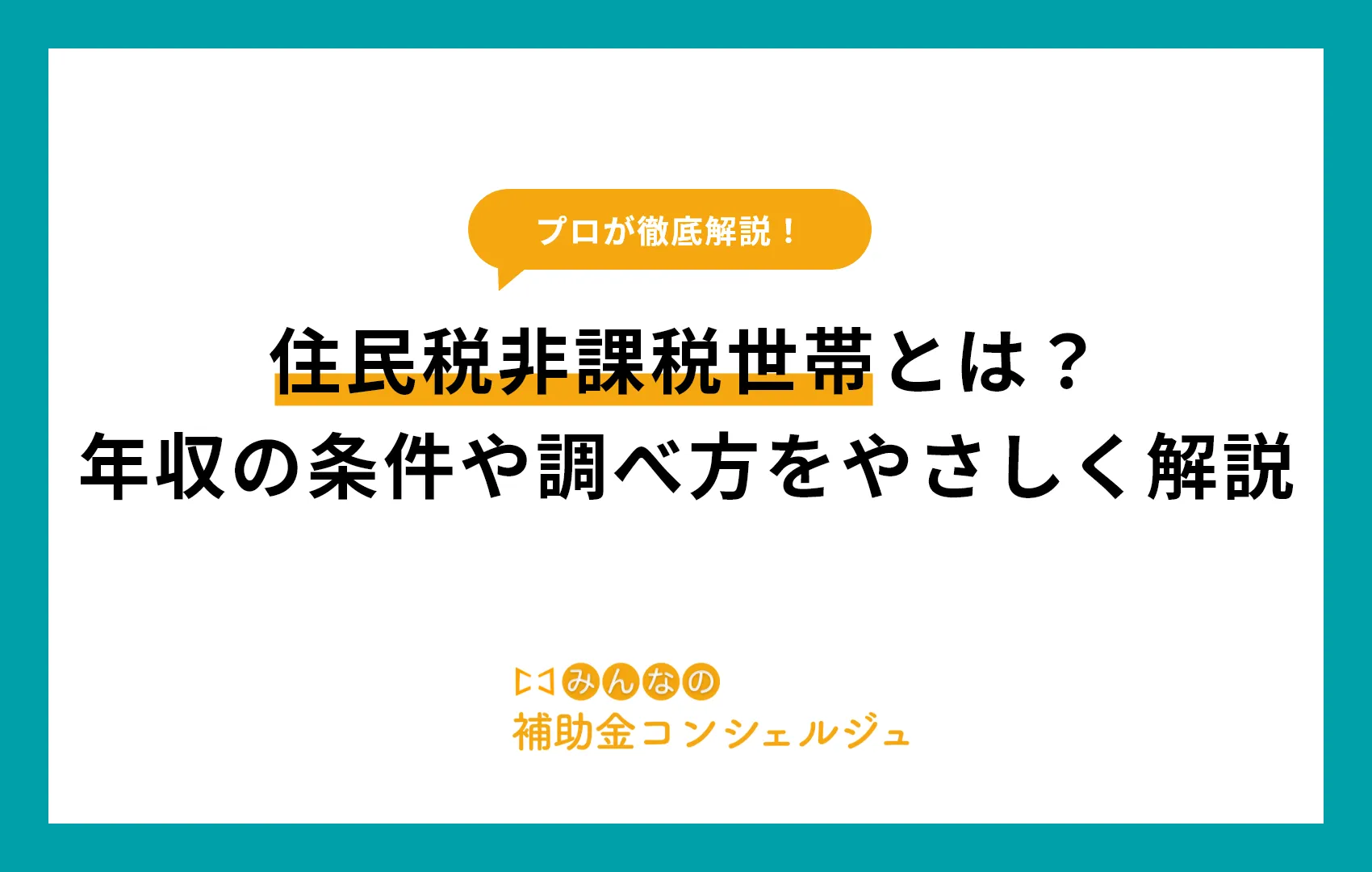
住民税非課税世帯とは?
住民税非課税世帯とは、「住民税が課税されていない人だけで構成されている世帯」のことをいいます。ここでは、そもそも住民税とは何か、そして非課税世帯になるとどうなるのかを、順を追ってやさしく解説します。
住民税とは?
住民税とは、「都道府県民税」と「市区町村民税」のことをまとめて呼んだものです。前年の所得(給料や年金など)に応じてかかる税金で、多くの人が毎年6月ごろから納めています。
住民税には、次の2つの部分があります。
| 種類 | 内容 |
| 均等割(きんとうわり) | 所得に関係なく、全員が同じ額を払う部分 |
| 所得割(しょとくわり) | 所得に応じて金額が決まる部分 |
参考:総務省「地方税制度の概要」
非課税世帯とはどういうこと?
非課税世帯とは、「世帯全員が住民税を課税されていない世帯」のことです。つまり、その世帯にいるすべての人が、住民税の「均等割」と「所得割」の両方がかからない場合に該当します。
たとえば、次のような方は住民税がかからない可能性があります。
- 所得が少なく、一定の基準を下回っている人
- 障害者、未成年、学生などで、一定の条件を満たしている人
- 年金収入だけで暮らしていて、課税基準以下の人 など
詳しい条件については、次のページが参考になります。
参考:港区役所「住民税の非課税に該当するのはどのような方ですか?」
非課税世帯になると何が違うの?
住民税非課税世帯になると、さまざまな支援や優遇を受けられる場合があります。たとえば次のようなものです。
- 国や自治体からの給付金(例:臨時特別給付金など)の対象になる
- 健康保険料や介護保険料が軽減される
- 医療費の自己負担割合が少なくなることがある
- NHK受信料が免除される場合がある
つまり、「住民税がかからない」こと自体が目的ではなく、「暮らしの負担が軽くなる」ことが重要なのです。
住民税非課税世帯の条件は?年収や家族構成で変わります
住民税がかからないかどうかは、「世帯の人数」や「扶養の有無」「年金の有無」などによって条件が変わります。この章では、住民税非課税世帯になる条件について、年収の目安や判定の基準時期とあわせて分かりやすく説明します。
世帯構成によって条件が変わります
住民税が非課税になるかどうかは、「一人暮らしか」「扶養している人がいるか」「高齢者世帯か」など、世帯の状況によって異なります。たとえば、以下のようなケースで条件が変わります。
| 世帯の例 | 条件のポイント |
| 単身世帯(ひとり暮らし) | 本人の所得が一定以下かどうか |
| 夫婦世帯(配偶者を扶養) | 世帯全体の合計所得が基準以下かどうか |
| 高齢者世帯(年金のみ) | 年金収入が一定以下であれば非課税になることがある |
年収や年金の目安
実際に「どのくらいの年収までなら住民税がかからないのか」を知りたい方が多いと思います。以下は、おおよその年収・年金の目安です。
【住民税が非課税になる目安(単身世帯の場合)】
| 状況 | 年収の目安(給与所得) | 年金収入の目安 |
| 単身で扶養なし | 約100万円以下 | 約158万円以下 |
| 高齢者(65歳以上) | 約100万円以下 | 約158万円以下 |
※給与所得と年金収入では計算方法が異なります。正確な判定には「所得控除後の課税所得」での確認が必要です。
※年金の目安は、年金収入が「公的年金等控除」を受けた後の所得で判定されます。
参考:総務省「地方税制度の概要」
いつの所得で判断されるの?
住民税の課税・非課税は、「前年の所得」で判断されます。たとえば、2025年度(令和7年度)の住民税は、2024年1月〜12月の所得をもとに計算されます。会社員の方であれば、年末調整や確定申告の情報から、自治体が自動的に判定を行います。年金受給者や無職の方も、一定の所得申告や扶養状況の申請が必要になる場合があります。
住民税非課税世帯になるとどうなる?もらえる支援や減免まとめ
住民税がかからない世帯になると、国や自治体からさまざまな支援や優遇を受けられる場合があります。ここでは代表的な以下3つの支援内容について、分かりやすくご紹介します。
- 給付金が受け取れることがあります
- 健康保険料や医療費が軽減されることがあります
- NHK受信料や介護サービスでも優遇があります
1. 給付金が受け取れることがあります
住民税非課税世帯は、政府が行う給付金の対象になることがあります。最近の例としては、2025年6月に石破首相が発表した「2万円給付金」が話題になっています。この給付金は、物価高騰などに対応するために支給されたもので、以下のような世帯が対象でした。
このように、住民税が非課税であることが給付金の受け取り条件になるケースが多いため、該当するかどうかを早めに確認しておくことが大切です。詳しくは、「2万円給付金」のもらい方や支給時期などは以下のコラムでくわしく紹介しています。
2万円の追加給付金はいつもらえる?対象者や申請方法をやさしく解説
2. 健康保険料や医療費が軽減されることがあります
住民税非課税世帯の方は、以下のような制度で負担が軽くなることがあります。
| 制度 | 内容 |
| 国民健康保険料の軽減 | 所得に応じて保険料が最大7割軽減されることがあります |
| 医療費の自己負担割合 | 高齢者医療制度で1割負担になる場合があります(条件あり) |
| 高額療養費制度の自己負担限度額 | 非課税世帯は、自己負担の上限が低く設定されます |
参考:厚生労働省|高額療養費制度を利用される皆さまへ
3. NHK受信料や介護サービスでも優遇があります
住民税非課税世帯になると、生活に関わるさまざまな費用で負担が軽くなる場合があります。代表的な制度は以下の通りです。
| 支援内容 | 概要 |
| NHK受信料の免除 | 条件を満たせば、受信料が全額または一部免除されます。 |
| 介護保険料の軽減 | 各市区町村の条例により、介護保険料が軽くなる場合があります。 |
| 上下水道料金やごみ袋代の減免 | 一部の自治体で、公共料金の減免制度があります。詳細はお住まいの市区町村にご確認ください。 |
参考:NHK|受信料免除の対象となる方について
住民税非課税世帯かどうかの調べ方|すぐに確認できる方法
「自分や家族が住民税非課税世帯に当てはまるのかどうか」を知りたい方は多いと思います。ここでは、すぐに確認できる以下3つの方法を紹介します。
- 確定申告や「住民税決定通知書」で確認する
- 自治体の窓口やコールセンターで聞く
- 年金生活者も自分で確認できます
1. 確定申告や「住民税決定通知書」で確認する
会社員や年金受給者の方であれば、毎年6月ごろに市区町村から届く「住民税決定通知書(課税・非課税証明書)」を確認しましょう。
- 「所得割」「均等割」ともに「0円」と記載されていれば、住民税非課税であることが分かります。
- 自分で確定申告をした方は、その控えを見ても「所得金額」や「課税額」で判断できます。
通知書が見当たらない場合は、自治体の税務課などで「非課税証明書」を発行してもらうことも可能です(有料または無料)。
参考:東京都港区「課税・非課税の証明書について」
2. 自治体の窓口やコールセンターで聞く
書類が手元にない方や内容がよく分からない方は、お住まいの市区町村の税務課または市民課に問い合わせをしましょう。
- 住民票の住所を伝えると、課税状況を確認してもらえることがあります。
- 必要に応じて、本人確認書類やマイナンバーカードの提示が求められます。
特に高齢の方や家族の代理で調べる方は、事前に「委任状」などが必要なケースもありますのでご注意ください。
3. 年金生活者も自分で確認できます
年金収入のみで生活している方も、自分が住民税非課税かどうかを確認することができます。
目安としては、
- 年金収入が158万円以下(65歳以上・単身の場合)
- その他の所得がない
というケースでは、住民税がかからない可能性が高くなります。
ただし、年金の「源泉徴収票」だけでは正確な判断が難しい場合があります。心配な方は、市区町村に「住民税非課税証明書」の発行を依頼するのが確実です。
住民税非課税世帯についてよくある質問
Q1. 自分が住民税非課税世帯かどうか、どこで確認できますか?
お住まいの市区町村から毎年届く「住民税決定通知書(課税・非課税証明書)」を見れば確認できます。
所得割・均等割の両方が「0円」になっていれば、非課税世帯と判断されます。
通知書が見当たらない場合は、役所の税務課で「非課税証明書」を発行してもらうこともできます。
Q2. 住民税非課税世帯の年収の目安はいくらですか?
年収の目安は、年齢や世帯構成によって変わります。
- 単身の方(65歳以上)の場合:年金収入が約158万円以下なら非課税になる可能性があります。
- 働いている方の場合は、給与収入が約100万円以下が目安です。
ただし、正確な判定は「所得金額」や「各種控除」によって異なりますので、不安な方は自治体に相談しましょう。
Q3. 65歳以上だと住民税は非課税になりますか?
65歳以上だからといって自動的に非課税になるわけではありません。
収入の金額が一定以下であれば非課税となるケースが多いという意味です。
たとえば、年金収入が158万円以下で、その他に収入がない場合は、非課税となる可能性が高いです。詳細は市区町村の窓口で確認してください。
Q4. 住民税非課税世帯になると、どんな給付金がもらえますか?
直近では、物価高対策として1世帯あたり2万円の追加給付金が実施されました。
こうした給付金は、国や自治体の判断で実施されるため、年度によって内容が変わります。
最新情報や申請方法については、以下のコラムで詳しく解説しています。
2万円の追加給付金はいつもらえる?対象者や申請方法をやさしく解説